"Contents"
勉強の内容
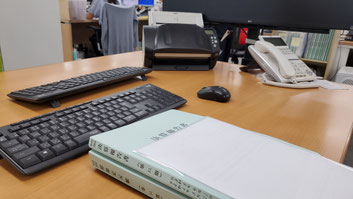
どんな勉強・研修・研究か
小さな事務所ですので大人数ではないのですが、それぞれ各人のニーズ・ 目標で何の勉強かは違います。
財務会計・簿記会計の基礎から勉強したい人・しなければならない人は、日商の 2級から始めます。
私達は日商簿記の2級を最良な勉強と考えています。
例えば日商簿記1級を勉強する人にとっても、2級をきちんと理解しきる事は 1級に進んだ時の土台になると考えていますので、分かったつもり、出来たつもりではなく、完全な理解まで行きます。
学習勉強の内容
❶日商簿記 2級 1年間隔月で、商業簿記と工業簿記を交互に実施します。
通常簿記の学校では3カ月から6ヵ月くらいで勉強すると思います。
私達は商業簿記を1か月、翌月は工業簿記を1か月と、交互に繰返します。
1回目で完璧に理解でき、2カ月で2級受験し合格する人もいます。
合格したけど、理解が不確かなのでもう一度勉強する人も又います。
1回目はまあまあ理解できたけど、もう一回勉強してもっとしっかり理解したいという人もいます。
通常簿記の学校では3カ月から6ヵ月くらいで勉強すると思います。
私達は商業簿記を1か月、翌月は工業簿記を1か月と、交互に繰返します。
1回目で完璧に理解でき、2カ月で2級受験し合格する人もいます。
合格したけど、理解が不確かなのでもう一度勉強する人も又います。
1回目はまあまあ理解できたけど、もう一回勉強してもっとしっかり理解したいという人もいます。
❷日商簿記 1級 1級は2か月商業簿記・会計学、次の2カ月は工業簿記・原価計算と交互に実施します。
受験学校では6ヵ月から1年のスケジュールでカリキュラムが組まれています。
私達は1回で理解出来るとも1回で合格するとも考えていませんし、きちんとした理解が大事だと考えています。
税理士試験の受験資格としての日商簿記1級合格とは別に、受験資格はある人に1級の商業簿記と会計学の勉強は勧めています。
例えば税理士試験の簿記論・財務諸表論は日商1級の商業簿記・会計学の範疇です。
その後の税法試験の総合計算問題にとっても、基礎の土台をバッチリ固める事は非常に有効と考えています。
受験学校では6ヵ月から1年のスケジュールでカリキュラムが組まれています。
私達は1回で理解出来るとも1回で合格するとも考えていませんし、きちんとした理解が大事だと考えています。
税理士試験の受験資格としての日商簿記1級合格とは別に、受験資格はある人に1級の商業簿記と会計学の勉強は勧めています。
例えば税理士試験の簿記論・財務諸表論は日商1級の商業簿記・会計学の範疇です。
その後の税法試験の総合計算問題にとっても、基礎の土台をバッチリ固める事は非常に有効と考えています。
❸税理士試験の簿記論・財務諸表論 上記でお伝えしたように税理士試験の簿記論・財務諸表論は、日商簿記1級の範疇なので、ベースは日商簿記1級の商業簿記・会計学の勉強と被っています。
プラスする事は、税理士試験の癖であったり、試験委員の考え方であったりのバリエーションの勉強と反復トレーニングと思います。
1級の土台がある人は、それで十分以上合格をします。
プラスする事は、税理士試験の癖であったり、試験委員の考え方であったりのバリエーションの勉強と反復トレーニングと思います。
1級の土台がある人は、それで十分以上合格をします。
❹税法(消費税・相続税・所得税・法人税) 上記4法を3カ月毎に変えて1年間を回します。
1回目2回目は初心者は、基本的な理解をして欲しいと思います。
それぞれの科目の受験生は、初心者に教えたり、自分の理解の不確かなところ、研究したい事を深堀すれば良いと思います。
税理士試験受験を想定して、そのまま受験勉強に突入してください。
1回目2回目は初心者は、基本的な理解をして欲しいと思います。
それぞれの科目の受験生は、初心者に教えたり、自分の理解の不確かなところ、研究したい事を深堀すれば良いと思います。
税理士試験受験を想定して、そのまま受験勉強に突入してください。
相続税・資産税(1月~3月) 1月~3月は相続税・資産税のサイクルで、確定申告時期で譲渡所得計算・贈与税の申告と重なり、確定申告時期は事務所の最繁忙時期です。
初心者は1回目、経験者は2回目3回目と理解の深度は違いますが、実務と条文がバッチリ噛み合う、分かり難い条文を実務から理解する期間かもしれません。
強制参加ではないので、仕事のスケジュールに気圧され参加出来ない人もいると思います。
原理原則と、その時の疑問や実際をテーマに進めます。
初心者は1回目、経験者は2回目3回目と理解の深度は違いますが、実務と条文がバッチリ噛み合う、分かり難い条文を実務から理解する期間かもしれません。
強制参加ではないので、仕事のスケジュールに気圧され参加出来ない人もいると思います。
原理原則と、その時の疑問や実際をテーマに進めます。
消費税(4月~6月) 4月~6月は消費税のサイクルです。
現在最も使用頻度の高い税法なのかもしれません。
課税なのか非課税なのか、国内なのか国外なのか、テーマも多い税目と思います。
会計科目の簿記論・財務諸表論から、税法を勉強するには消費税を勧めています。
税法の勉強の仕方、条文の読み方のトレーニングをします。
必修税目よりボリュームが小さく、条文を読む練習をするには合っていると思います。
現在最も使用頻度の高い税法なのかもしれません。
課税なのか非課税なのか、国内なのか国外なのか、テーマも多い税目と思います。
会計科目の簿記論・財務諸表論から、税法を勉強するには消費税を勧めています。
税法の勉強の仕方、条文の読み方のトレーニングをします。
必修税目よりボリュームが小さく、条文を読む練習をするには合っていると思います。
法人税(7月~9月) 7月~9月は法人税の勉強サイクルです。
8月には税理士試験が有りますので、別の税法を受験したり、会計科目を勉強する人はそれぞれの勉強をしています。
来年以降受験したい人や、法人税の全体像を理解したい人は参加し、改正のトピックや良くあるパターンの理解を進めています。
税理士試験に合格したい人は必修税目の一つですし、毎月毎月の法人決算と直結するし、財務会計との親和性も高い税目と思います。
税法試験の最難関、ボリュームも最大の税法科目です。
8月には税理士試験が有りますので、別の税法を受験したり、会計科目を勉強する人はそれぞれの勉強をしています。
来年以降受験したい人や、法人税の全体像を理解したい人は参加し、改正のトピックや良くあるパターンの理解を進めています。
税理士試験に合格したい人は必修税目の一つですし、毎月毎月の法人決算と直結するし、財務会計との親和性も高い税目と思います。
税法試験の最難関、ボリュームも最大の税法科目です。
所得税(10月~12月) 10月~12月は所得税の勉強サイクルです。
ちょうど11月12月の年末調整、年明けの確定申告と勉強学習と実務・仕事が繋がる時期と思います。
法人税と同じく必修選択科目の一つです。
私達は税理士試験合格の必修科目を一つ選ぶとすれば所得税を勧めています。
若い人は必修2科目もチェレンジングで良いと思いますが、スタートが遅かったり家庭を持って受験をする人には、所得税をお勧めしています。
所得税の中のテーマが幾つもありますので、勉強もし易いと思います。
ちょうど11月12月の年末調整、年明けの確定申告と勉強学習と実務・仕事が繋がる時期と思います。
法人税と同じく必修選択科目の一つです。
私達は税理士試験合格の必修科目を一つ選ぶとすれば所得税を勧めています。
若い人は必修2科目もチェレンジングで良いと思いますが、スタートが遅かったり家庭を持って受験をする人には、所得税をお勧めしています。
所得税の中のテーマが幾つもありますので、勉強もし易いと思います。
その他 例えば税法の受験をする人も、しない人も、上記の各期間はそれぞれの税法の原理・原則の勉強を中心に、その時のテーマだったりトピックスを勉強します。
税理士試験を想定してそのまま受験体制で勉強をしている人もいるし、基礎固めとして勉強する人もいます。
税理士試験を想定してそのまま受験体制で勉強をしている人もいるし、基礎固めとして勉強する人もいます。

